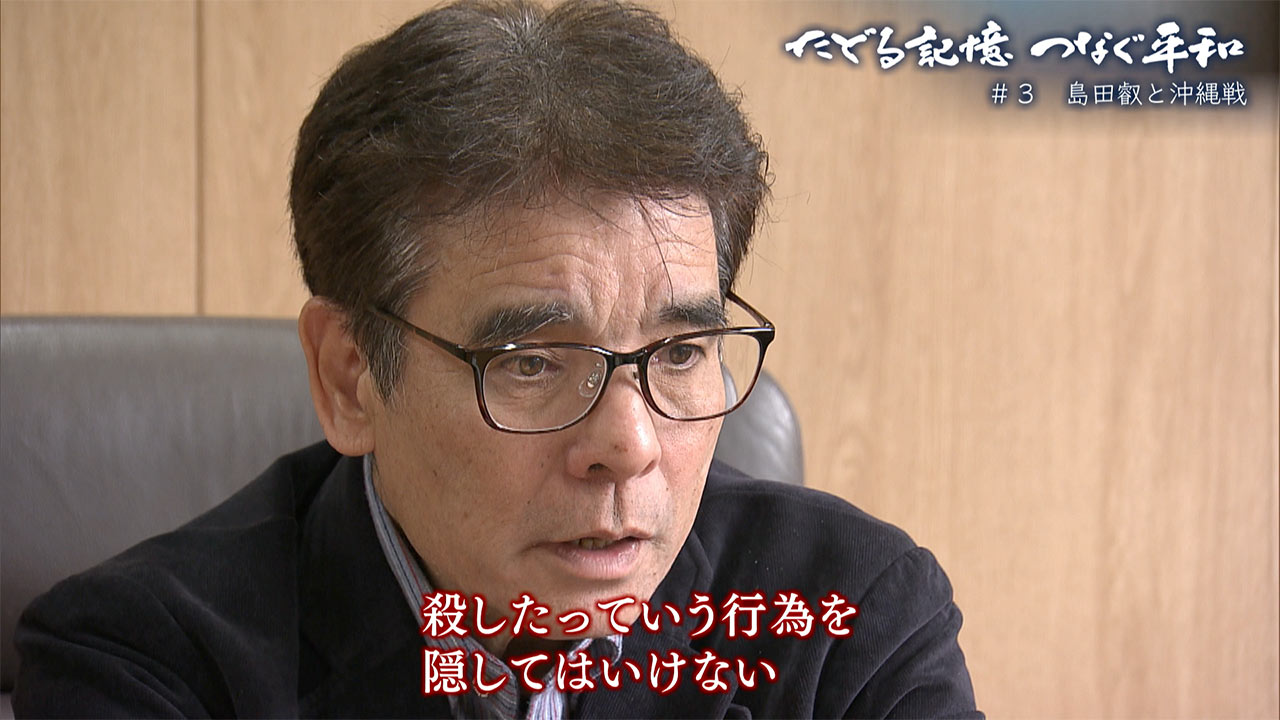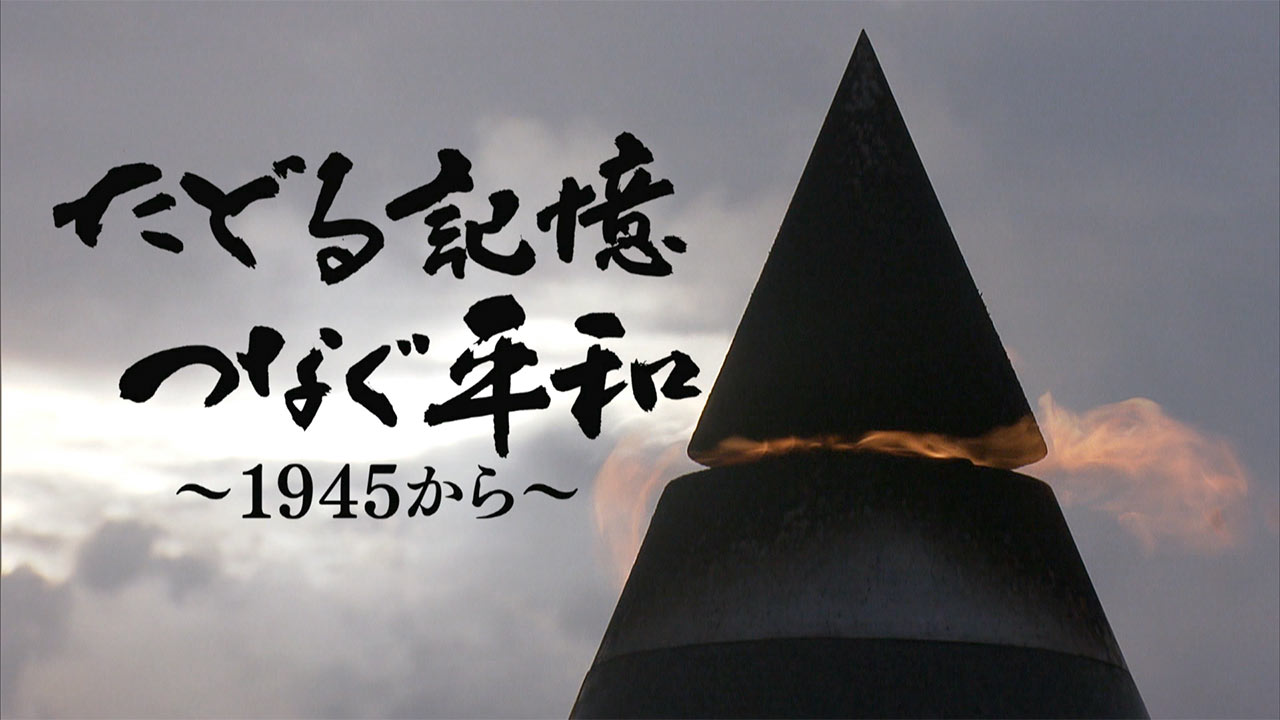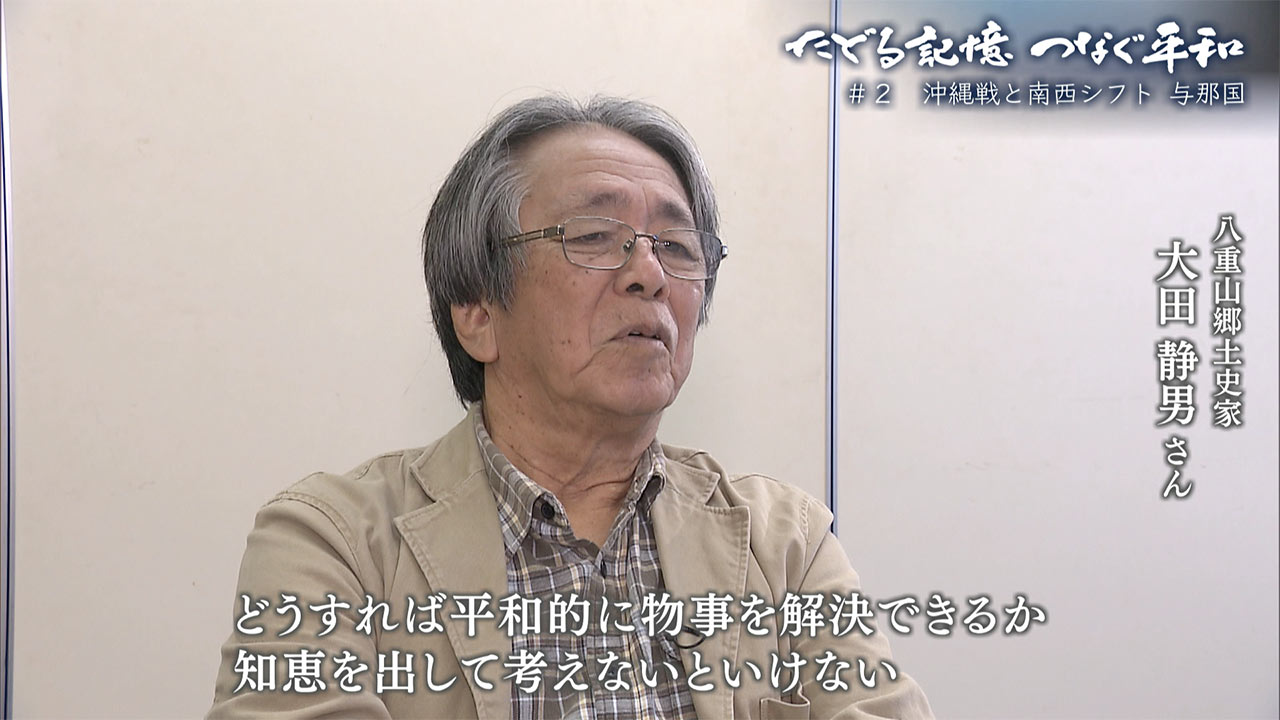戦後80年の節目に戦争について考えるシリーズ「たどる記憶・つなぐ平和」です。今回は、沖縄へのアメリカ軍の上陸直前、1945年の1月と2月の状況について振り返ります。
アメリカ軍や日本側で戦争計画が決まってきたのもこの時期で、3月に始まる地上戦の足音は、確実に近づいていました。
2010年、QABが放送した年間企画「オキナワ1945 島は戦場だった」を一部再構成してお送りします。
アメリカの首都、ワシントンDC近郊にある、合衆国海兵隊戦争記念碑。硫黄島(いおうとう)の戦いで星条旗を掲げる兵士をモチーフにした像の台座には、数々の戦場の名が刻まれ、その中に「OKINAWA」の文字もあります。

そのアメリカ軍が沖縄への上陸作戦の計画を立てたのは、1945年1月6日のことでした。作戦の名は氷山を意味する「アイスバーグ」。この年の3月までに、沖縄を占領して軍事基地を置き、日本に圧力をかけることを作戦の主眼に置いています。
日本側でも、アメリカ軍の沖縄上陸を想定した動きも出てきます。1月、日本政府は「沖縄県防衛強化実施要綱」を決定。県民の総力戦、食糧の増産、住民の疎開や立ち退きなどの方針が決まります。

総力戦の方針を受け戦意を高める動きも出てきます。1月末、沖縄に駐屯していた第32軍の長勇(ちょう・いさむ)参謀長は、新聞の談話でこう呼びかけていました。
「軍の指導を理屈なしに素直に受け入れ、全県民が兵隊になることだ」「一人十殺 これでいけ」
2月18日、県内の各中学校では「防衛隊」も組織されました。

神谷依信さん「生命は羽毛より軽いんだと」「当時の軍国主義の教育というのは、僕らが小学校に上がってからは」「全部そういう風にして仕向けられているわけですよ」
首里高校の前身、県立第一中学校出身の神谷依信(かみや・よりのぶ)さん。3年生だった神谷さんは鉄血勤皇隊の通信隊員として、沖縄戦に参加しました。15歳から17歳の生徒たちが軍事訓練を経て、戦場へと送り出されていったのです。
2010年、QABのカメラは、後輩にあたる首里高校の生徒に体験を語る神谷さんの姿を、収めていました。
神谷さん「1500隻の軍艦で真っ黒になっていた。海の色が見えないくらい」首里高の生徒「自分だったら耐えられないです」「今、勉強とか部活動に一生懸命取り組めることがとても幸せなことだと実感した」

この時期、沖縄本島のみならず離島や先島地域も含めて、アメリカ軍の空襲が激化。久米島の儀間港では、2月14日、軍用船3隻が空襲を受け沈められています。目撃していた男性の証言が、QABのライブラリに残っています。
宮城幸信さん「やられて、炎上して、丁度見たら船尾の方で船員が消火しているのを」「もうすぐ目と鼻の先。びっくりして山に逃げてね」
軍用船は軍に徴用されていた漁船でした。アメリカ軍は前年の10・10空襲以降、南西諸島の島々で軍の施設のみならず、港などの施設も攻撃対象にしていたのです。
宮城さん「(船が)どこからともなく、入ってきて、また出ていくものだから、どこへいくのかなと子ども心に思っていたんだけれども、儀間港から兼城港まで輸送船がいっぱいしておったんだよ」「中継地点になっていたんでしょうね」
3月に慶良間諸島。4月に沖縄本島への上陸が始まり、地上戦が行われていく沖縄戦。その前夜ともいえる45年の1月と2月は、学徒も含めて動員が進む中で、空襲の被害も増え続けていました。

この時期に決められた日米の戦争計画に沖縄県民は巻き込まれ、翻ろうされていくことに、なるのです。
沖縄戦の前夜ともいえる時期に、日米の作戦の計画が決まってくるわけですが、「一人十殺」の言葉に代表されるように、日本軍にとって県民は守る対象ではなく、作戦を進めるうえで、利用する対象でしかなかったといえます。
QABでは、過去に取材した証言も生かしながら、沖縄戦の実態をお伝えしていきたいと思います。