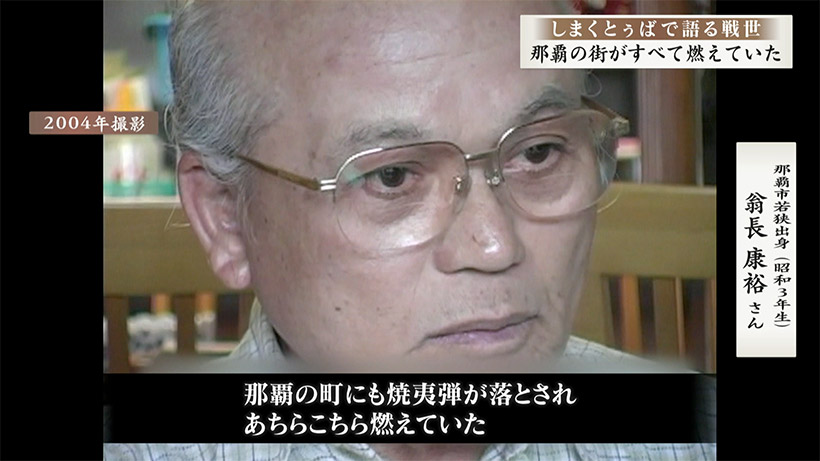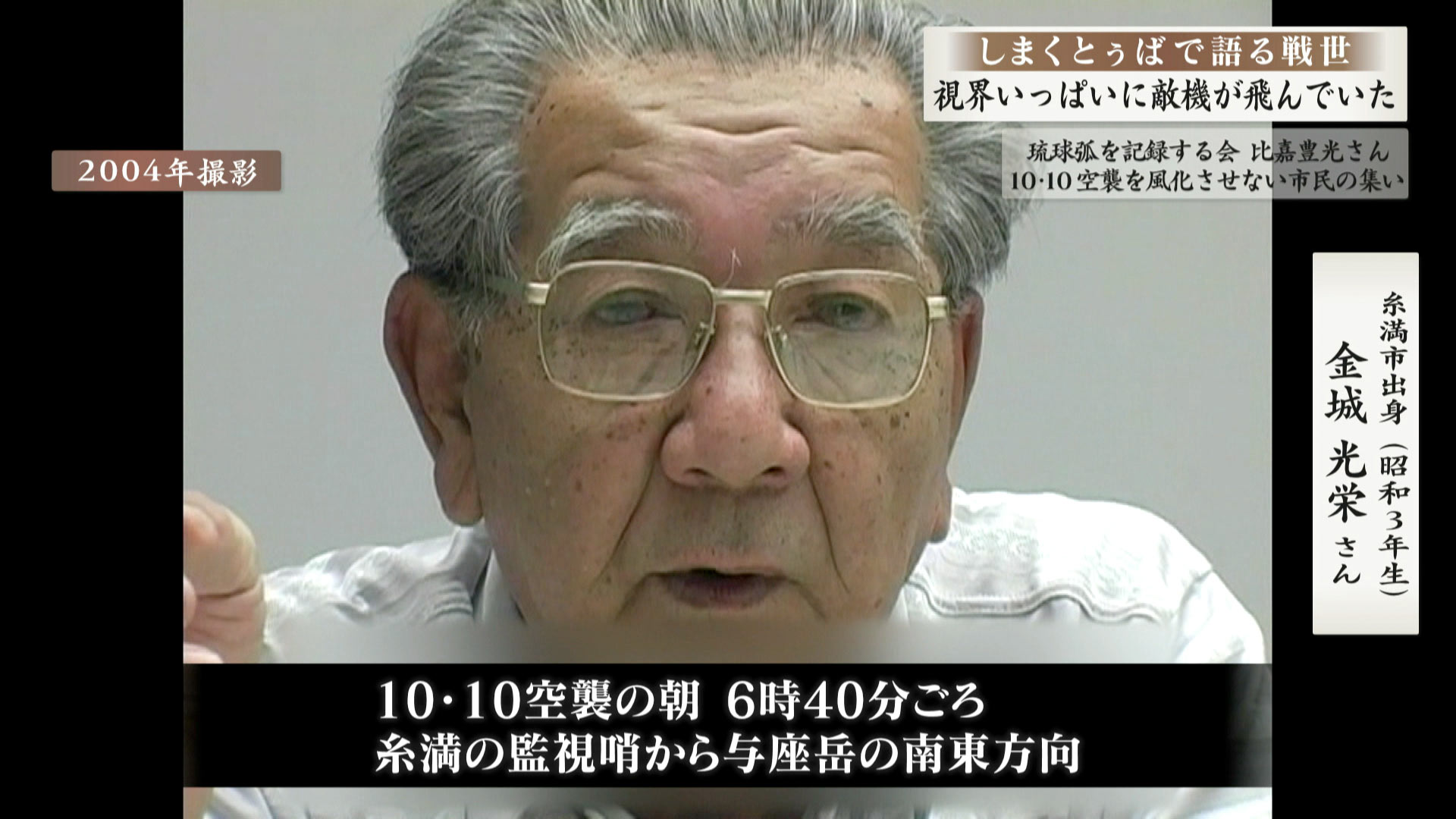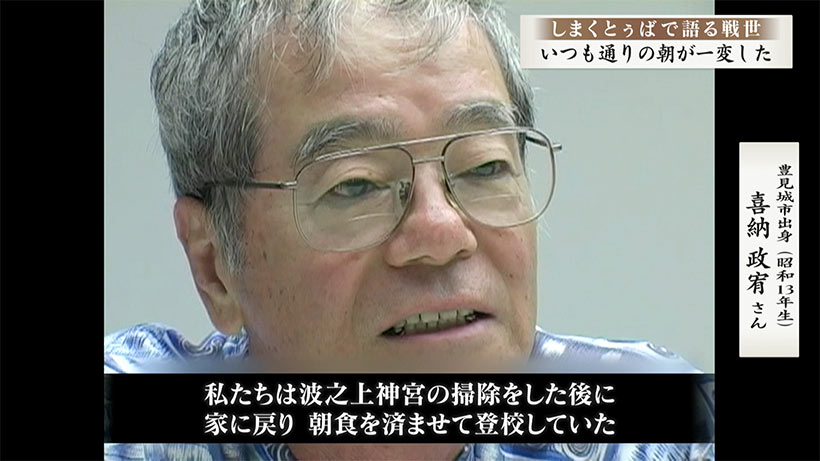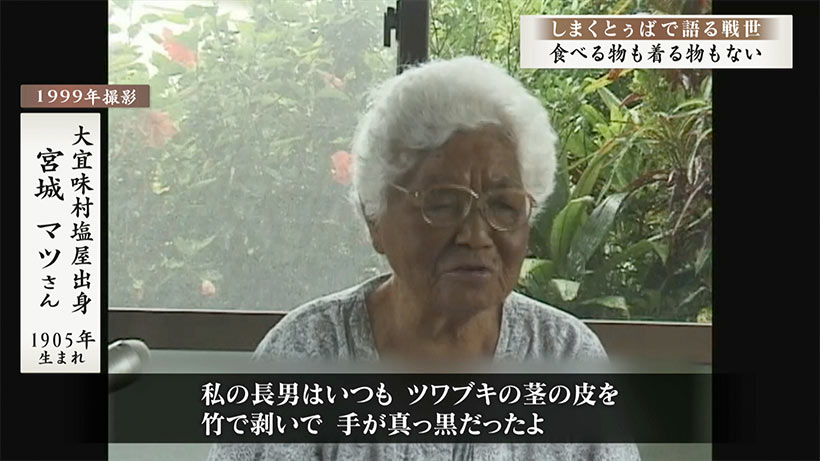※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。
シリーズ「たどる記憶 つなぐ平和」です。80年前のきょう、アメリカ軍が上陸した翌日の4月2日、ガマでは住民が死に追い込まれる、いわゆる「集団自決」が相次ぎました。
読谷村にあるチビチリガマでは、およそ140人が避難していて、「アメリカ兵に捕まると残虐な仕打ちを受ける」と恐れていました。人々は自決するしかないと考え、住民83人の命が失われました。
一方で、避難者のほとんどが助かったガマもあります。
2つのガマでは、なにが起こっていたのか…「しまくとぅばで語る戦世」から当時の出来事を振り返ります。まずは「チビチリガマ」についてのお話です。
このチビチリガマから歩いて20分ほどの場所に「シムクガマ」という洞窟があります。ここにはおよそ1000人が避難していて、チビチリガマと同じように集団自決をしようと考える人が多くいましたがあることがきっかけで、状況が変わります。
一体どんなことが起きていたのでしょうか?「シムクガマ」のお話です。チビチリガマでは、「生きて捕まるな」という空気の中で集団自決が起き一方、シムクガマでは、言葉が分かる人がいたことで、アメリカ兵との対話が生まれ、多くの命が救われました。
これだけ近くの壕にいて、同じように恐怖の中にいた人々の運命が少しのきっかけで分かれたことを思うと、胸が締めつけられます。戦争の悲惨さと、命の重さを改めて考え語り継がなければなりません。